
「あたらしい音楽」を発掘・発信するヂラフマガジンが、2024年の活動に注目したい期待のインディーズアーティストを発表。音楽の趣味嗜好も年代も異なるライター7名が1組ずつ厳選し、それぞれの感性で魅力を綴った。
この時期さまざまなメディアで「今年のバズ予想」が発表されるが、本マガジンはよりディープなラインナップで、各ライターが心から推せる原石アーティストをいち早く紹介。ジャンルや国の垣根を越えて、「あたらしい音楽」との出会いをぜひ楽しんでいただけたらと思う。
各ライターが2023年のマイベスト曲をセレクトしたヂラフアワード2023もぜひチェックを。
不思議な魅力のある歌声で、世界を鮮やかに彩っていく
みぃなとルーチ
『夜の魔物』
みぃなとルーチは、声以外の情報が一切公開されていない覆面音楽ユニット「さよならポニーテール」のメインボーカル・みぃなのソロ・プロジェクト。
「夜の魔物」は、2ndアルバム『Waiting for the moon to rise』に収録されている、直接心に触れるような揺らぎのある繊細な歌声と、独特のワードセンスが光る歌詞が印象深い楽曲だ。
終電を逃した時に「それじゃあしょうがない」と夜の街をぶらつくときの、突発的に発生した非日常を面白がるひそやかな喜びと、ひとりでいることの安らかさを感じる。
ガード下のグラフィティーに指を這わせて、歩道橋の階段に貼られた様々なステッカーをひとつひとつじっくり見る。誰もいないのをいいことに夜道を小さくスキップして歩く。
みぃなとルーチの曲を聴くと、孤独は毛嫌いするものでも遠ざけるものでもなく、じっくり味わっていいものなのだと思えるし、帰る場所などあってもなくても同じだという気持ちにもなる。心の中で、大丈夫、とはっきり思う。
何が大丈夫なのかもわからないのに、大丈夫だと思ってしまうのだ。寂しくても悲しくても、楽しくても楽しくなくても、大丈夫だと。
明確なファイトソングじゃないのに、聴くだけでなんだか妙に勇敢になってしまう。そんな不思議な歌を歌うアーティストとして、これからの活動にも注目し続けたい。
(文・望月柚花)

強く優しく響く、寝屋川ロックバンド
ハニカム
『ひまわり』

大阪の数あるライブシーンでも特に目の離せない、ライブバンドを定期的に全国へ輩出するロックな地域、寝屋川。そこで活動する期待の1組がハニカムです。
まず、寝屋川らしいと言ったらアレですが、ライブハウスでの爆音も似合う真っ向勝負なライブバンドです。
そして彼らは、放課後の穏やかな夕暮れの日差しや、最寄り駅に向かう何でもないアスファルトの道といった、日常へのフィット感がとてもあります。
だからこそ、ふと日常の中で頭によぎる不安や寂しさに対しての効力が強いです。「そうだよな、こうやって成長していくんだよな」と思わせてくれるのが随一だと。
そんな温度感を感じていたタイミングで公開された『ひまわり』のMVが良い。やっぱり穏やかにオレンジがかる空との相性が良いし、ミディアムバラードでここまで伝わっていくバンドは数少ないと思います。
そしてライブも見たんですが、25分でもとてもドラマチックに感じました。10代の彼ら、これからどんどん深まるバンドサウンドを出していくでしょう!
ちなみに、2023年の最注目アーティストとして紹介させていただいたバンド、ちゃくら。当時はまだライブも数えるほどだった若手でしたが、2023年は全国で100本を超えるライブを行い、飛躍したんじゃないかなーと思ってます。
なので今年のチョイスにも期待してもらって大丈夫です!
(文・遊津場)
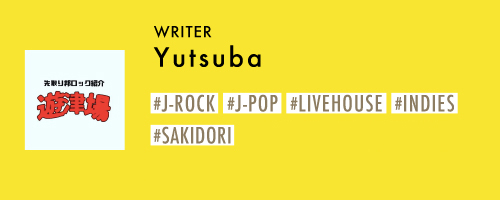
2024年に絶対にバズる、自他共に認める“天才”なシンガーソングタイター
Kentaro
『Soda』
– 缶開ける音で曲作ってみた-より

「待って! ヤバい!!」
から始まり、缶を開ける音やオーブンの音と楽器を組み合わせて音楽を紡ぐショート動画を見たことはないだろうか?
天才シンガーソングライターのCharlie Puthが音楽の制作過程を載せて「ノリと思いつきで神曲を作っていく」というショート動画があるが、同じフォーマットで音楽を次々と制作するKentaroもまた自他共に認める“天才”である。
「勝手に車のCM曲を作ってみた」「勝手にコナンの主題歌作ってみた」などユーモアもあり、かつそのテーマに合致した中毒性の高いフレーズをコンスタントに産み出し続けるKentaro。その多くがショート動画で完結するためにワンフレーズのみ制作・公開となるのだが、続きを所望する声も少なくはない。
そのショート動画で公開された中でもフルで制作されたのが『Soda』という曲である。炭酸の缶を開ける音にインスピレーションを受けて制作された楽曲だが、「炭酸」というモチーフが持つエモさを「炭酸」という言葉を使わずにここまで表現できた音楽はかつてあっただろうか。
またショート動画の効果もあってか「いつ炭酸の缶を開ける音が来るかな」というワクワク感もあり、SNSのトリックがよく仕掛けられた楽曲となっている。
彼の動画スタイルや才能を鑑みるに、そう遠くないうちにかなりのバズが起きそうな予感がする。2024年は、その瞬間を楽しみにして彼の動向に注目していきたい。
(文・宮本デン)

“令和世代”の青春パンク!
the奥歯’s
『鈴鳴メモリーズ』

2024年に注目したいバンドは、広島県出身、アサベシュント(g,vo)、アサベハルマ(b,vo)、ジン(ds,cho)の3名からなるパンクバンドだ。
2021年の1stシングルを皮切りに、ツアーやイベント、フェスなどで着実に名を広げている。2023年3月には、初の全国流通版1stミニアルバム『夜の住人』をリリース。
楽曲の「激しさ・時に聴かせる綺麗なメロディ・がむしゃらさ」は、1990年代に大流行したGOING STEADYを感じさせる。
彼らの激しさは楽曲だけではない。熱量の高いライブパフォーマンスも彼らの人気の理由だ。ライブ中の勢いや熱量を見れば、今30代~40代で、当時青春パンクに夢中になった人も、確実に心を動かされるだろう。
とくにおすすめの楽曲は、ミニアルバム『夜の住人』の6曲目に収録されている「鈴鳴メモリーズ」。どこか懐かしさを感じるメロディと、青春の情景を思い出させる歌詞、それでいて精一杯歌う姿は心に突き刺さる。
「青春パンクバンドが好きだったあの頃」「恋愛にも趣味にも夢中だったあの頃」、そんな大人の心までえぐるthe奥歯’sは、また同じように、若い世代の青春になること間違いないだろう。
(文・名城政也)

NYジャズシーンで躍進する台湾人ヴィブラフォン奏者
チェンチェン・ルー(Chien Chien Lu / 魯千千)
『We Live in Brooklyn Baby』
2023年2月に劇場公開され、大ヒットを記録した『BLUE GIANT』。この映画を観てジャズに興味を持った方も多いのではないだろうか。
原作の最新シリーズで、主人公が遂にジャズの聖地ニューヨークにたどり着くが、そのニューヨークで頭角を現しはじめたアジア人ヴィブラフォン奏者がいる。
台湾出身のチェンチェン・ルーは、母国でクラシックを学び、フィラデルフィア芸術大学ジャズ科でヴィブラフォンを専攻。2017年よりニューヨークを拠点に活動する。
グラミーの「注目すべき新進ジャズアーティスト10人」に選出された2023年、彼女は2枚のアルバムを発表した。
1月13日にリリースされた『Connected』は、ベーシストのリッチー・グッズとのコラボアルバム。アフリカ系アメリカ人のグッズとアジア人のルーが、人種問題について意見を交換していくうちにアルバム制作がスタート。メッセージ性の強い本作は、“中華圏のグラミー賞”と呼ばれる「金曲奨」でベスト・インストゥルメンタル・アルバム賞を獲得している。
10月6日には、ヴィブラフォン、トランペット、ベース、ドラムとのカルテットでライブレコーディングした『Built In System』をリリース。クロスオーバー路線の『Connected』から一転して、ストレートアヘッドなジャズを展開している。
デビュー作『The Path』(2020年)も必聴。台湾の音楽アワード「金音創作獎」でベストジャズソング賞を受賞したタイトル曲や、彼女が敬愛するロイ・エアーズの名曲「We Live in Brooklyn Baby」のカバーをぜひ聴いていただきたい。
(文・五辺宏明)

彼らの姿を見ると音楽の面白さを思い出す
urei
『マジックアワー』

「音楽の根源的な面白さは、声を出すことや楽器を奏でることにある」
そんなことを思わせてくれたのは、福島県いわき市発の日本語ロックバンドureiだ。
ureiはVo./Gt. 草野寛太、Ba./Cho. もひお、Dr./Cho. ひろむの3人からなる3ピースロックバンドで、2022年に2nd EP『愛し愛されて』、2023年に3rd EP『STAND BY YOU』をリリースするなど、精力的に活動している。
冒頭でも書いたように、彼らの音楽からは「バンドってやっぱり楽しいよなぁ」というような楽しさが感じられる。
彼らが純粋に楽器を演奏する姿、全員がサビを笑顔で歌い上げる姿を見て、はじめてギターに触れたときの感動や、はじめて人前で演奏したときの高揚感と緊張、楽器を始めてこれまでに味わってきた感情が込み上げてきたからだ。
楽曲を聴くだけで元気が出るし、演奏する姿を見ると笑顔になれる。そのような想いになれるのは、彼らがバンド活動を本当に楽しんでいるからだからだと思う。彼らの姿を見てバンドをやってみたいと思う人が増えると思う。それくらいに彼らの演奏が好きになっていた。
来年は絶対にライブハウスで、拳を高く上げながら彼らとともに笑顔でこの曲を歌ってみたい。
(文・竹内将真)
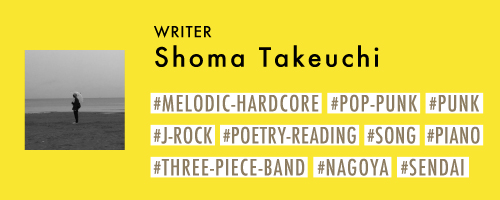
Z世代バンドが掻き鳴らす、“痺れる”ロックンロール
The Muddies
『Satisfied?』

親しみやすいビジュアルと、日常を描いた等身大の楽曲。そんな近年の音楽トレンドにあえて逆行するように、彼らはストライプのスーツ姿でステージに立ち、ガレージロックやブラックミュージックを彷彿とさせる楽曲をどデカい音で掻き鳴らす。
往年の音楽をただなぞるのではない。さまざまな音楽性を複雑に絡ませ、ときに引き算の美学を魅せつけ、アグレッシブでエンタメ性もあるライブパフォーマンスで客を沸かせる。嫌でもバズを意識してしまうこの時代に、「自分たちのロックンロールを貫く」という離れ業を飄々とやってのける、それがThe Muddies(ザ マディーズ)だ。
シカゴ・ブルースの父、Muddy Watersをバンド名にするという渋い感性をもちながらも、メンバーはまだ20代前半。小学生のころからThe Beatlesの話で盛りあがっていたというFUTA(Vo./Gt.)とKOMEI(Ba.)を中心に、 FUTAの兄のISSEI(Gt.)、URARA(Dr.)の4人で活動している。
2018年、FUTAが高校3年のときに『出れんの!?サマソニ!?』ファイナリストに選ばれ、秋山黄色やHue’sらとともにSUMMER SONICに出演。2023年にはRISING SUN ROCK FESTIVALの若手オーディション『RISING★STAR』を勝ち抜き、若さと貫禄を兼ね備えたエネルギッシュなステージを北の大地で披露した。
彼らの音楽に抱く感覚をものすごくうまく表現しているワードを、『Satisfied?』のMVのコメント欄で見つけた。
「痺(シビ)れる」。そうそう、それだ。死語すぎて忘れていたけれど、なんて言い得て妙なんだろう。2023年に稀代のスーパーロックヒーローが旅立ってしまったが、90年代に彼の音楽と出会って抱いた感覚もまさに「痺れる」そのものだったことを思い出す。
2024年も、The Muddies流のロックンロールに思いきり痺れたい。1月末にリリースされる新曲も楽しみだ。
(文・三橋温子)







