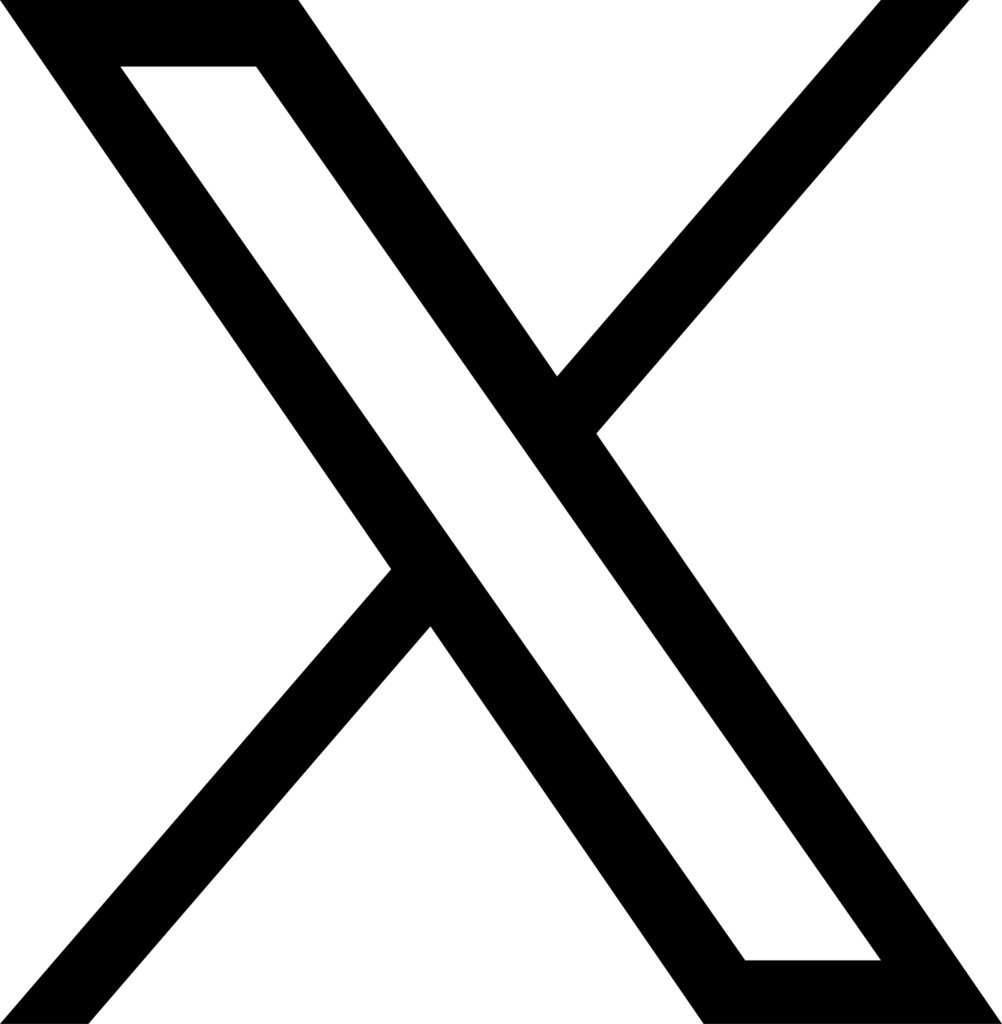2022年に活動をスタートした東京発のロックバンド・VIYON(ヴィヨン)が9月13日(金)、東京・下北沢ReGにて『世のなか、人の中』を開催した。
8月末に活動を再開したVIYON完全復活の狼煙を上げる同ライブには、VIYON、ノユイ、蜃気楼、アウフヘーベン、Swing by Sing、メメの6組が出演。対バンを重ねてきた盟友から念願の初対バンを果たした新たなライバルまでが、祝祭ムードの中で火花を散らしたライブの様子をお届けしよう。
Swing by Sing
借りたギターに込められた友情
この日のトップバッターを務めたのはSwing by Sing。石井丈(Vo,Gt)の甘酸っぱい声色が感傷的な恋心を映し出す『メッセージ』でライブをスタートさせると、石井のカッティングにもってぃー(Ba)のスラッププレー、ワウの効いた滝澤諒(Gt)のギターが重なり、『Someday』へ雪崩れ込む。
途中、石井の弦が切れるというハプニングがありつつも、ほりうま(メメ・Gt,Vo)の赤いセミアコを借りてライブを続行。ライブハウスで醸成されてきた友情が垣間見える出来事に、対バンライブならではの魅力をひしひしと実感する。
「根暗な人間だから、死にたくなることもある。僕が音楽を聴いて頑張りたいと思ったみたいに、誰かに頑張りたいと思ってもらえる音楽を作っていけたら」と告げ、投下されたのは『Blue』。
自問自答するような序盤から田中勇多(Dr)のビートに合わせて中盤で加速すれば完全にネジは外れ、残すはブッ飛ばすのみ。滝澤は激しくギターを掻き鳴らし、もってぃーと石井は相対しながら目を見開いて煽りに煽る。右肩上がりにパワフルになる演奏は、内省的な同ナンバーの主人公が次第に今日を肯定できるようになっていく変化とシンクロしていた。
ラストナンバーにセレクトされた『many…』では、ベースソロをかましたもってぃーがピースサインを決めるお茶目な一面も。バキバキのサウンドでコーティングされた瑞々しいナンバーたちが、鮮烈なインパクトを残した1番手だった。
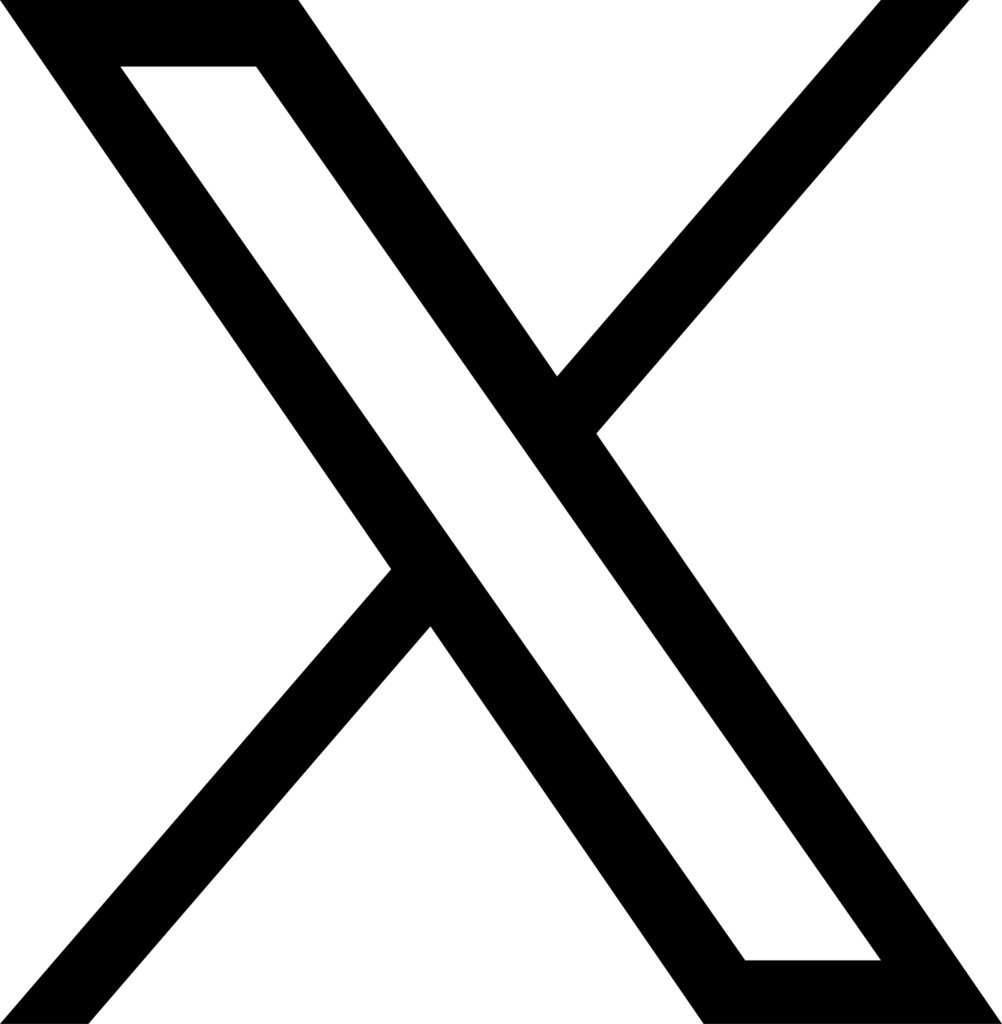
アウフヘーベン
特別編成で鳴らしたロックバンドを続ける理由
紗幕が上がり、アウフヘーベンのステージが始まる。かと思えば、ぐま(Gt)がこう告げた。「いつも俺らは4人なんですけど、3人で。今日一番格好良いライブして帰ります!」――大胆不敵な宣言とドカンと鳴らした一撃で特別編成の幕を上げると、『時代によろしく』でタイトル通りの先制攻撃。
ライブ中盤、ぐまが「あいつ(Gt,Voむろ)がいなくてどこまでできるか。ボーカルがいないからってステージに立つ理由は変わらない。いろんな理由が浮かぶけど、ロックバンドやる理由は1つしかないんすよ」と叫ぶと、『ボーイズ・ミーツ・バンド』をドロップ。下北沢を舞台に夢を追う姿とリアルな生活の隙間を描いた同曲がこの場所で鳴ることによって、ハコや街に眠った酸いも甘いもを呼び覚ます。
〈ボーイズ・ミーツ・バンド〉と叫ぶぐまと近藤(Ba)、大夢(Dr)の姿は、惹かれ合う少年少女に言葉が要らないように、「なぜロックバンドに魅せられているのか」という問いに対し「出会ってしまったから」と即答するような純真さを体現していた。
エンディングを彩ったのは『暮らしについて』。『ボーイズ・ミーツ・バンド』の曲中、ぐまは「僕とVIYONが知り合ったのは2年前のReGなんです」と語っていた。ライブハウスや街で生まれた無数の記憶が堆積し、暮らしを形作っていく。「優しい歌」と紹介された『暮らしについて』がフロアを満たしていく光景を見て、時と共に薄れていくあの日を思い出すよすがが歌なのだと考えさせられる。
この先どんな思い出が待ち受けているのか。過去だけでなく未来にも思いを馳せたくなる25分だった。
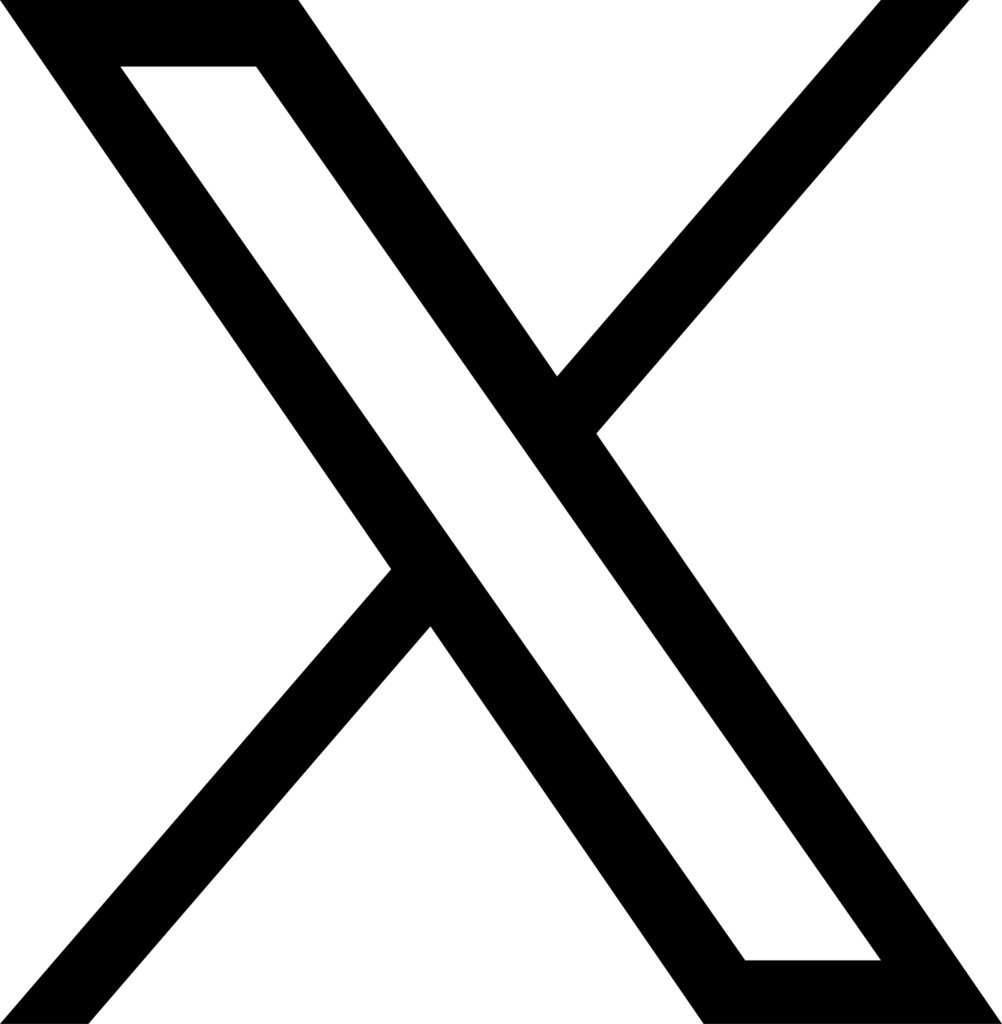
蜃気楼
幸せの糸を手繰り寄せて
3番手の蜃気楼は、爽やかなギターと共にあんでぅー(Ba)が飛び跳ねた『8割主義』でキックオフ。凛としたという形容がドンピシャなももせ(Vo,Gt)の歌声が、回り始めたミラーボールと絡み合いダンスフロアを出現させると、ローな質感の声色が印象的な『星を渡って』、アタック感の強いあんでぅーのスラッププレーが炸裂したアッパーな新曲を畳みかける。
ももせは今回の企画名に触れた上で、「人間は1本の糸でみんな繋がっていると思うんです。その1本の糸が幸せだと思っています。たとえ細くてもそれを大事に、幸せに生きられますように」と話す。
祈りの込められたMCから披露されたのは『幸せを追いかけて』だ。スモークがたっぷりと焚かれた舞台上で、スポットライトを浴びながら叫び上げるももせの背中は、手を伸ばさないと消えてしまう不確かな幸福を抱きしめるようだった。
ラストに鳴らされたのは、バンドの名を冠した1曲『蜃気楼』。繊細なイントロからボリュームを上げて爆発すれば、フロアは拳で応答する。これにはひとん(Dr)も笑みを浮かべ、ももせもハウリングギリギリの声量で負けじと応戦。相乗効果で熱を帯びていく会場は、「ライブかくあれ」と思ってしまうほどの理想形であった。
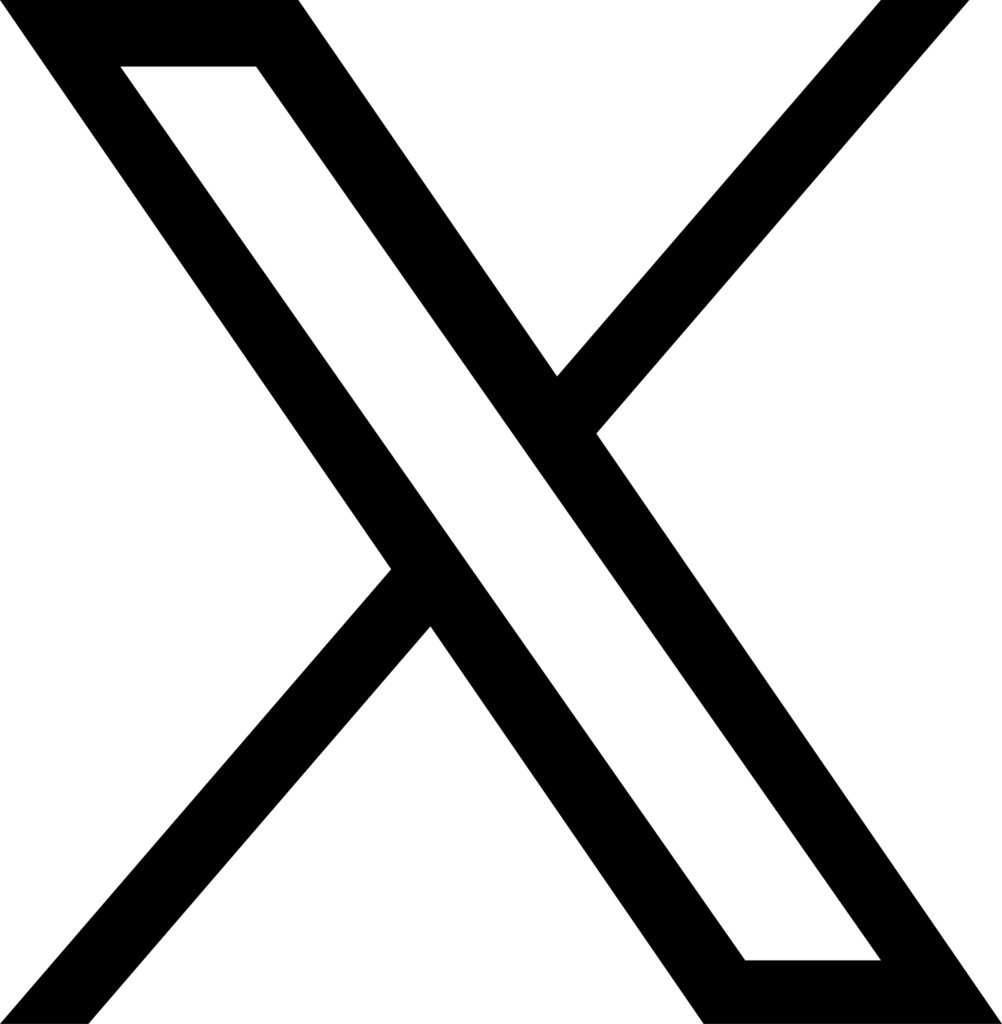
メメ
一口で分かる至福のメロディー
時報をミックスしたSEが告げるのは、メメのショータイムの始まりだ。ちゃる(Dr,Cho)の掛け声を号砲に幾発か掻き鳴らしたのち、大地乃愛(Ba,Cho)が客席にグッドマークを早速お届け。ほりうま(Gt,Vo)が「お力添えを! クラップ!」とアジテートして、『モンキーモンキーモンキー』で滑り出す。
ラウドなパートから大地のラップ、4つ打ちのダンスナンバーまで目まぐるしく曲調が変化していく一方で、一聴で口ずさみたくなる〈モンキーモンキーモンキー〉の一節が人懐っこさを演出する。
その親しみ深さは続く『ノースキャロライナ』でも顕著であり、複雑に絡み合うリズムやコーラスワークも馴染みやすいメロディーによって楽々と消化できてしまう。
「涙を流しても許される場所の歌」と称された『shower room』は、メランコリックな大地のボーカルとすがりつくようなほりうまのラップが並行していく構成が特徴的。
2人がユニゾンする〈私…三日坊主なの〉のラインは、一方にとっては過去に言われた台詞として、もう一方にとってはたった今呟いた言葉として響く。もう交わることのない2人の様子を劇中劇がごとく台詞の形式で表現する手腕は見事であり、3人全員がボーカルとしての側面を持つメメの魅力を最大限に発揮していると感じた。
「一度無くなったものを復活させるのには労力がかかります。何があってもこのステージで会おうという約束の曲」と投げかけ、フィナーレを締めくくったのは『メロスのひとりごと』。ほりうまの「またこのライブハウスで会おうぜ」という咆哮が、再会の約束としReGに刻まれた。
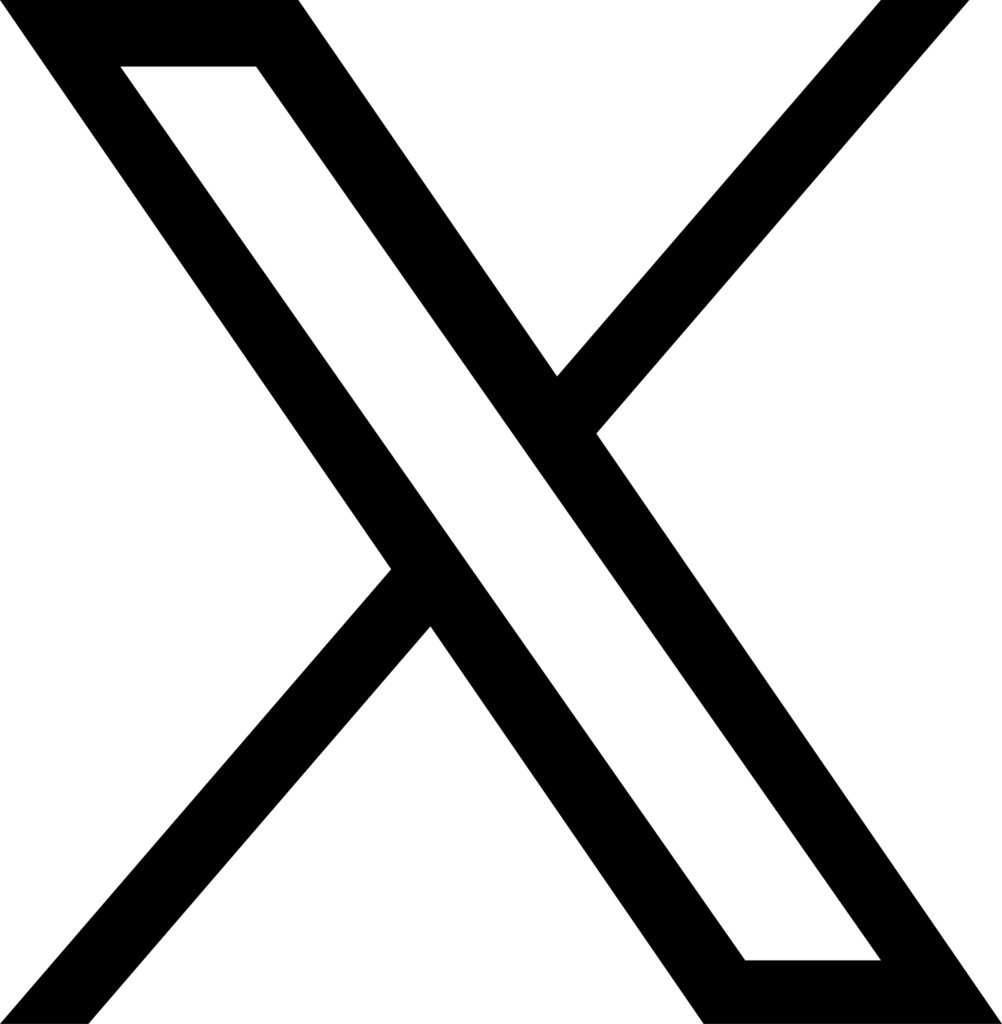
ノユイ
これがノユイの最新
最終走者のVIYONに直接バトンを渡すのはノユイだ。サイトウ乃唯(Gt,Vo)の甘い一声が求心力を持つ『弱者の革命』で幕を切り落とすと、会場は早くもハンズアップ。この段階で4バンドが作り上げた空気をノユイが受け継いでいること、そして彼らのエッセンスを加えてVIYONへと託そうとしていることが読みとれる。
サイトウのブリッジミュートが生む灰がかったトーンが取り留めのない日常を固定化した未発表曲、石黒トモヤ(Ba,Cho)の勝ち気な音像がトレードマークの『再会』と、未リリース曲を畳みかける。
VIYONへの感謝を告げた後演奏された『日々、愛おしく』も、3カ月連続リリース第1弾の楽曲であり、現在のノユイが持てる全てをぶつけていることは明白。これからのノユイの歩みにも期待を寄せたくなる中盤戦であった。
クライマックスは、ライブハウスで生まれる縁を綴ったアンセマティックな『この場所で』から、「VIYONの明日は俺たちが照らす!」という布告と共に『明日を照らせ』へ雪崩れ込む。初期衝動という言葉に還元することができない、刹那的に魂を燃やす美しさが確かに存在していた。
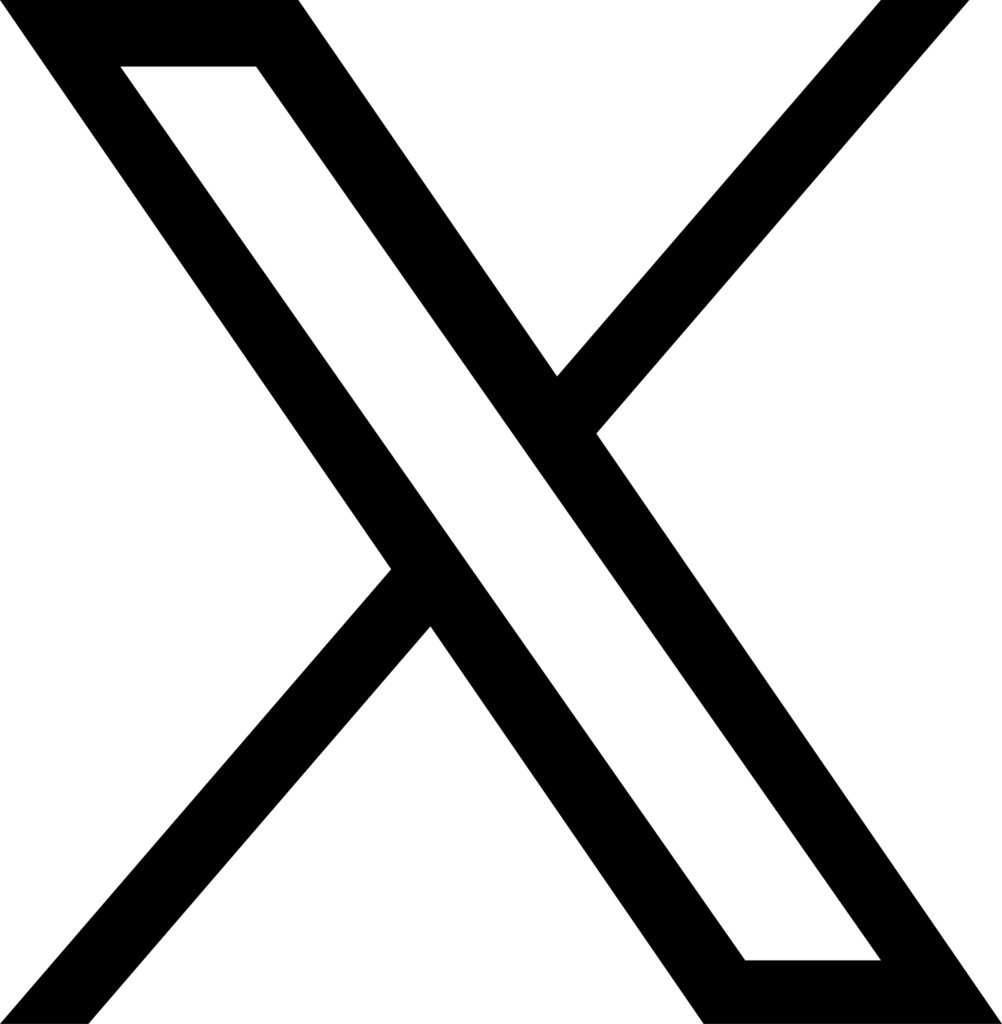
VIYON
VIYON完全復活!
約5ヶ月の活動休止を経て、VIYONが完全復活! 『アメイジング・グレイス』をSEに荘厳な雰囲気の中登場した4人の背中には、白いバックドロップが鎮座している。
「VIYONです。よろしく」と簡単な挨拶から、シューゲイザーの系譜さえ感じる轟音が身体を包む。『星と熔岩』で鮮烈なオープニングを迎えると、『SARU PLAN(plan B)』を連投。ギターソロを炸裂させる齋木碧(Gt,Cho)はフロアへと乱入し、久方ぶりにステージに立つことができた喜びを全身から滲ませる。

アルペジオが重なっていく中ぼんやりと緑のライトが灯り始め、幻想的な光景を建設した『ミドリ』を経て、スカからラウドまで軽さと重さを自由に横断する『正体不明』、クラップが湧出した『ワンダー』と最新曲を連打し、クライマックスまで突っ走っていく。
変拍子や各パートのソロを織り交ぜ、カテゴライズから逸脱しながらも王道性を失わないVIYONの楽曲群は、4人のテクニカルな演奏はもちろんのこと、瑞々しさと不安定さを両立するホリエ(Vo,Gt)の存在によって支えられているのだろう。

ライブ終盤、ホリエはイベントタイトルについてこう語った。「今の時代は怖い人が見えやすい時代だと思う。悪い面が見えてしまう時代の中、社会を作っているのは人。どんな世の中も作るのは人で、どんな人でも優しくあってほしい」。
この時代で生きていくことの難しさと尊さが込められたMCから齋木のアルペジオにホリエのギターが重なり、うさ(Ba)と関戸(Dr)がアンサンブルに加入すると、『日蝕』でしっとりとピリオドを打った。アンコールでは、ローポジションで展開されるリフのユニゾンが印象的な新曲『father3』を披露。再び歩み始めたVIYONの行く末に胸が高鳴る。


1日を通じて感じたのは、イントロやアウトロ、各パートのソロを積極的に組み込んでいるバンドが集っていたということ。ファストに楽曲を味わうことができるようになった現代において、簡単には食べきれない(しかし、味わい深い)音楽を6組は提供していたのである。
こういったバンドが一堂に会することができたのは、ひとえにVIYONが簡単に消費できない音楽を作ってきたこと、また普遍的な楽曲を志向してきたことの表れだろう。
そもそもライブハウスという手間暇のかかる空間は、ある意味ではファストと対極なのかもしれない。しかし、この場所で生まれた繋がりの糸や記憶は深く深く刻まれていくのだ。